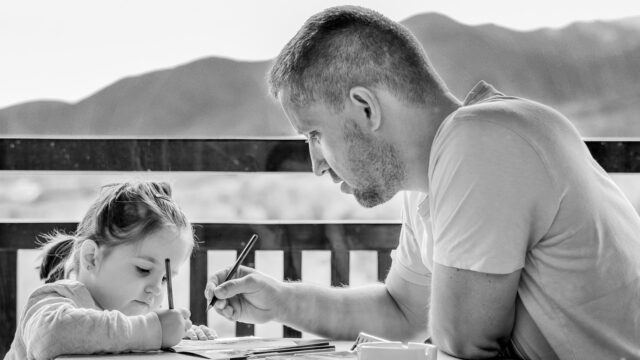子供の褒め方について悩まれてる方は多いのではないでしょう。
私も同じです。よく「褒めた方が良い」「褒めて育てよう」というフレーズは目にしますが、実際問題どのように褒めればよいのか考えてみました。
褒め方の種類は大きく3種類。褒め方のポイントは4つ
実際に私もよく使用している褒め言葉にも3種類に分けられると考えました。種類を抑えれば自分の言動がどれに当てはまるか考えることが出来ます。それを踏まえた上で褒め方のポイントについても学びましょう。
3つの褒め方。
褒め方は大きく分けて3つの種類があると考えます。
1.表面的な褒め方
例「すごいね!」「上手!」
2.その子供の性格や能力等外面部分にフォーカスした褒め方
例「天才だね!」「優しいね!」
3.努力や過程にフォーカスした具体的に褒める褒め方
例「頑張って最後までやりきったね!」「色んな色を使って描けたね!」
具体例を挙げてみます
サッカーの試合でスタメンを勝ち取った子供がいたとします。
その際、「すごいすごい!」と褒めるのが1.の表面的な褒め方
「センスあるからな〜」と褒めるのが2.の外面部分にフォーカスした褒め方
「スタメンになるまでにいろんな努力をしてきたね」と褒めるのが3.の努力等にフォーカスした褒め方
1.2の褒め方つまり具体性に欠けて外面的な部分にだけフォーカスする褒め方は良くない褒め方なように見えますね。
実際自分が言われても「本当に思ってる?」と勘繰るかもしれません。
アパレル店で試着した際、自分ではしっくりこないけど店員さんに「お似合いです!」と言われるようなイメージですね。
3.の過程にフォーカスして具体的に褒めるのが良く見えますね。
結果はどうあれ、そこまでの過程を見てくれてたことを嬉しく思います。
自分が会社の上司にそのように励まされればまた頑張ろう!という気になりますよね。
具体性に欠けて外面部分にフォーカスする褒め方は良くないのか
それは、ただ漠然と褒める行為により、以下の弊害をもたらす可能性があるからです。
1.「褒められる」ということだけを求めるようになる。
何かの行動が「褒められる」という目的のための、ただの手段になってしまう可能性があります。
本当は自分が興味を持って始めたことなのに、評価が気になり、結果や過程より最後の評価ばかり気にして楽しくやれなくなりますよね。
2.新しいことにチャレンジしにくくなる。
結果について褒められることだけを求めてしまうと、新しいことや苦手な分野には「結果が出ず褒められないかもしれない」と思ってしまいかねません。
自分自身も会社で、「君は優秀だから新しい営業先を一任するよ!」なんて言われたら返ってプレッシャーになり新しいチャレンジなんてしにくくなってしまいますよね。
子供もきっと同じ感覚を持つと思います。
3.頑張る意欲が低下する。
努力の有無に関わらずなにをしても「すごい!」と褒めてしまうと、努力をして何かを成し遂げる意味を見し出せなくなってしまいます。
また努力などしなくても褒められると気づいてしまえば、ただその行動を終わらせることだけにフォーカスしてしまい、工夫等は見れなくなってしまいかねません。
褒め方のポイント
良くない褒め方が整理できたところで、次は褒め方のポイントを確認してみましょう。
褒め方は4つのポイントがあります。
- 結果より過程を
- 具体的に
- 会話をするように
- 共感する
それぞれ詳しく見ていきましょう
1.結果より過程を
行動の結果や、能力ではなく、努力や工夫した取り組みについて言及しましょう。
「褒める」というよりは、「励ます」の方がイメージしやすいでしょうか。
具体的には、テストで100点を取ったことに対して「すごい!」というより「100点を取るまでいろんな勉強方法を試したね」と伝えることです。
もし、努力の過程等が見えなかった時は見ていないのに伝えるのではなく後述する3つのポイントを意識してみましょう。
2.具体的に
ただ漠然と「すごい!」というだけではどこが良いのか、またどのようにすればもっと良くなるのかイメージできないですよね。
例えば子供がたくさんの色を使って描いた絵を見せてきたとします。
それに対して「すごい!」だけでは味気ないですね。それに対して「たくさんのいろを使って描いたね!特にこの赤と黄色の混ざっているところは華やかでいいね!」と言われると良く見てくれてるな。と子供でも感じるはずです。
この「具体的に」というのをわかりやすく置き換えると「見たままをそのまま伝えてもあげる」ということです。
良く見てあげて見たままに伝えてあげましょう。そうすれば「すごい!」という口癖から脱却できるはずです。
3.会話をするように
「褒める」意識が強いとどうしても大人側から何か伝えなければと考えてしまいますが、子供からの意見を上手く引き出すのも褒める行為の一種だと思います。
上手く引き出すために「YES」「NO」で答えられる質問はせず、自由な回答ができるものにしましょう。
ここでも絵を描いた子供が見せてきたことを想定します。
そこで「これはなにを描いたの?」や「なぜこの色にしたの?」など質問することで子供の意見を自由に引き出せることができます。
引き出したものから更に掘り下げていけば子供は充分自分を見てくれてる。と感じるはずです。
4.共感する
最後はこの「共感」です。
子供が何か成果物を見せてくる時は、それの評価を求めてるのではなく、共有がしたいだけのパターンがほとんどだと思います。
大人も同じだと思います。何か新しい発見や嬉しい出来事があると誰かに話したくなるものです。
そんな時は無理に何か評価するのではなく子供の思いを受け止めて共有しましょう。
本当にすごいと思ったら「すごい!」でもOK!
「すごい」の言葉がダメなのではなく、具体性にかける闇雲な「すごい」がダメなので大人が本当に感心したことには素直に自分の気持ちを伝えましょう!
まとめ
- 褒める時は具体的に!
- 結果よりも過程にフォーカスして!
- 見たままを伝えて更に質問して子供の意見を聞き出す!
- 評価より共感を!
以上となります。
あくまでこれは1つの指針です。
正解がない子育ての中で皆さんのモヤモヤの解決策になれば幸いです。
楽しく、後悔のない子育て生活を送りましょう!